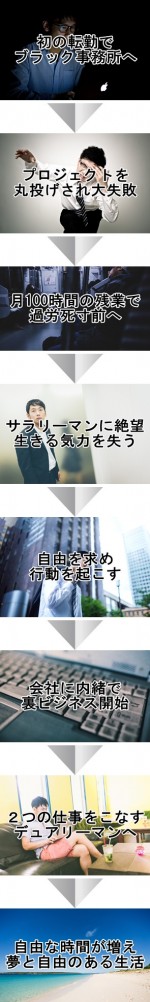夢を叶えるための行動
Facebook攻略の勉強会に参加

J PROJECTの月1勉強会に参加してきた。
テーマは「Facebook攻略」。
僕はFacebookのことは
知っていたつもりだった。
でも、わかっていなかった。
その差に気づけた日だった。
僕は過去にFacebook集客の
講座に1年近く通ってたことがある。
Facebookで集客はできてたし
売上も上がっていた。
全て理解しているつもりだったが、
今日のFacebook勉強会は学びばかりだった。
「目的のない投稿は絶対にしない」
Facebookの投稿には
2つの種類がある。
それが
①ポジショニング投稿
②パーソナリティ投稿
もちろん知っていたし
意識はしていたつもりだった。
でも今の僕の投稿を見返すと、
「この投稿の目的はなんだ?」
というものが多々ある。
この投稿は友達やフォロワーに
どんな気持ちになってほしいのか。
その先に、
どんな一歩を踏み出してほしいのか。
これらに答えられないのであれば
投稿する意味がない。
これは新たな気づきだった。

「コメント返しはいつやるか?」
Facebookを戦略的に運用していると
「どうやったらリーチが伸びるか」
「エンゲージメントがアップするか」
とかに考えが行きがちである。
今日の勉強会では、
「コメントはすぐに返信があった方が嬉しいのでは?」
という講師の言葉があった。
ハッとした瞬間である。
アルゴリズム的な正しさより
人としてのやさしさが先にあるということ
「自分がされて嬉しいことを、先にやる」
なるほどと感心させられた。
「毎日更新を、毎日貢献に」
正直に言う。
僕は1日1投稿という投稿数を
ずっと守っていた。
「今日も1投稿できた」
と満足していた。
でもそうじゃない。
その投稿をみて
受け取った側は何を感じるのかを
考えたことがあるか?
投稿を読んだ方が
・少し心が軽くなった
・背中をそっと押された
・小さくても行動が動いた
こんな姿を想像して、
投稿を書けてただろうか。
初心に立ち返ることができた。

「出来事だけを書いてないか」
そこに「自分の気づき」を与えると
投稿に心がこもるということ。
僕という人間を感じてもらうことができる。
・なぜ、その出来事にハッとしたのか
・自分の過去のどこに刺さったのか
・これから、何をやめて、何を始めるのか。
この3つを添えるだけでも、
文章に感情が芽生える。
そして読む人の自分ごとにも、
つながっていく。
これに加えて、
読みやすさは、相手への礼儀であること。
Facebookの読み手のことを考えて
読みやすい文章になっているか。
・例えば短い行で改行しているか
・冒頭2行で興味を引いているか
・自撮りの写真はいれているか
・メッセージは1つになっているか
これはテクニックではない。
相手の時間を尊重する姿勢だと思う。
ちょっとした心がけで
やさしい文章になることが分かった
「投稿にバリエーションを持たせる」
・価値提供・・・悩みが少し軽くなる気づき
・社会的証明・・現場の声や歩みの実感
・導線・・・・・必要な人が迷わず辿り着ける道筋
・人となり・・・好き嫌い、価値観、弱さも含めた等身大のこと
これらの投稿が
バランスよく散りばめられてないといけない。
今後のFacebookの投稿では、
以下のことを意識していきたい。
①2行の見出しで興味付け
目的のない投稿は一切しない。
これは読者の時間を守るため。
②投稿文は、出来事 → 気づき → 結論で書く
投稿には型がある。出来事を書くだけでは意味がない
自分の気づきを必ず入れていくこと。
③投稿する前に
「誰に・何のために」を
必ず確認する。
④コメントの返信は早く返す
相手が嬉しいから早く返す。
画面の向こうにいるフォロワーのために。

「Facebookどおりの人であること」
僕はFacebookでは顔出しをしていない。
なぜなら会社員であるため
表立ってビジネスができないためである。
顔が出せない分、
Facebookの運用は慎重にならないといけない
Facebookから僕のセミナーに参加してもらったとして
実際に僕と合った時の印象が
Facebookでの印象と一致しているか。
そのために
パーソナリティ投稿がある。
自分の人柄を知ってもらうことが
目的の投稿である。
そこで自分を良く見せようと
自分を無理して誇張表現していると
現実とのギャップが生まれる
つまり、普段の投稿は
「等身大の自分」
であることが絶対条件である。
顔を出していない中で
信用してもらうことが難しいことは
重々承知している。
今後もパーソナリティ投稿は
等身大を意識してやっていきたい。

「学びの場への感謝」
J PROJECTに入会して半月。
膨大なカリキュラムに圧倒されながらも
自分の必要と思うカリキュラムから
徹底的に学んでいる。
今回、J PROJECTに入会して感じたのは
環境の大切さである。
今回のFacebook勉強会もそうだが
受講生の意識が高い。
質疑応答の時間も
受講生からの質問が途切れない。
僕がこれまでに参加した講座では
ありえなかったこと。
学びは素晴らしい環境の中で育つ。
だから、前を向ける。
だから、続けられる。
僕はこの環境を最大限に生かし
成果を上げていく。
それがJ PROJECTへの恩返しであり
僕自身の成長にもつながるから。